のどかな風景が広がる奥越の高原と
かつて鉱山があった大野市南部の秘境を訪ねる |
|
|
|
 |
今回は冬期閉鎖解除と同時に土砂崩れによって通行止めになっていた国道157号の温見峠が通行可能となったので、いつもの根尾越波経由にて奥越を目指す。
ただし根尾越波から大河原までの猫峠林道が土砂崩れによって、今だ復旧しておらず、市道にて黒津を経由する。 |
| 折越林道開設記念碑には、猫峠林道通行止めの案内があった。 |

|
|
|
 |
市道を黒津に向かって南進して福井方向とは逆行するので少し遠回りになる(15分くらい)
やがて根尾西谷川の向こうに国道157号が見えてくる。 |
| 黒津の手前で橋にて左岸に渡り、国道157号に合流する。 |
|
| |
|
 |
恒例の温見峠。
手前に能郷白山登山者の車が数台駐車してあった。
天候が良好なこのシーズンには、数十台もの車の駐車を見かけることがある。
|
| 県境から福井県に入ってすぐのところ。 |
|
| |
|
 |
温見峠はあまり展望のよいところはないが、峠から福井県側に少し下ったところに唯一と思われるビューポイントがある。
回を重ねてようやく見つけた。
福井県側に大きくカーブする国道が眺望できる。
あらためて温見峠の峻厳さを感じるのである。
※ビューポイントは車から降りて、路肩ぎりぎりに寄らないと見えない危険な場所につき注意。 |
一カ所のみ、このような峠から眺望の良い場所がある。
普通は気付かずに通り過ぎてしまう。 |

|
| |
|
 |
上記の眺望のよいところを探そうと思っても、峠の谷側にはガードロープすら設置していないところ多し。
|
そっと路肩を覗いてみる。
停車後に見る方が怖く感じるのは何故だろう ? |
|
| |
|
 |
国道157号の麻那姫湖青少年旅行村近くに、以前より気になっていた銀杏峰(1,440m)への中島側登山口がある。
舗装路からすぐに荒れたダートとなり、バイクですら走行できない登山道となる。 |
国道157号から西へ入る林道が銀杏峰中島ルート入り口となる。
別名「親水古道」というらしいが、荒廃が進んでいるようだ。 |

|
| |
|
 |
いつもの麻那姫湖青少年旅行村にて宿泊。
真名川ダムから麻那姫湖の東側沿いの林道を経由して、かつてモリブデン鉱が産出されたという仙翁谷(せんのうだに)まで行く。
真名川ダム管理棟手前からダム堤端を渡り、林道上若生子・中島線を南下する |
| 時間が早いのでダムに人の気配はない。 |
|
| |
|
 |
真名川ダム天端は自動車の通行が可能。 |
| あいにくの小雨模様で緑が映えない。 |
|
| |
|
 |
ダムを渡ると、ダム工事で殉職された方々の慰霊碑を右手に見ながら林道は中島側へ戻る方向となる。 |
数名の方が殉職されたようである。
合掌。 |
|
| |
|
 |
真名川ダムから林道上若生子・中島線を15分くらい進むと、コンクリート製の橋を渡り、道はT字となって左右に分かれる。右へ行くと若生子大橋のたもとを通って大野市中島へ至る。
左へ入る道が仙翁谷から更に奥まで続く林道。 |
| 林道上若生子・中島線の真名川ダムより2つ目の橋となる。 |
|
| |
|
 |
橋を左折するとすぐに、仙扇谷の管理区分を表記した朽ちかけた看板が左手に見える。 |
| いまにも倒れそう。 |

|
| |
|
 |
仙翁谷から無名の林道を更に奥へと進む。
情報では、このあたりにかつての鉱山跡となるズリ山(掘った土の捨て場所)があるはずだが、場所が何処なのかわからない。
それに、中竜鉱山の「仙翁谷抗口」も近くにあるのだが、同じく場所が特定できない。
|
| このあと林道はダートとなって東に延びる。 |
|
| |
|
 |
注意深く抗口を探しながら進むも、同好の方のサイトで確認しておいたそれらしき場所が見当たらない。
それとも支線の林道から辿るのだろうか?
|
| 小雨の中を名の知れぬ林道を進む。 |
|
| |
|
 |
仙翁谷の看板のあったところから30分ほど来たところで林道は通行止となってしまった。
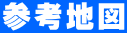
ここで諦めて引き返し、次の目的地「六呂師高原」へとバイクを走らせる。 |
| ゲートにて封鎖でされ、その先は獣道化している。 |

|
| |
|
 |
大野市街から国道158号を白鳥方面に向かい、大野市下唯野から福井県道239号に入り六呂師方面へ進む。 |
| 雨は止んだが曇っていて、レインスーツを脱ぐタイミングを考えながら走る。 |
|
| |
|
 |
福井県道26号に突き当たるので、右折して六呂師・勝山方面へと進路をとる。
道は徐々に高度を上げてゆく。 |
| のどかな田園風景の快走路を行く。 |

|
| |
|
 |
福井県道26号から六呂師・勝山方向へ聳える山々が見える。 |
| 今回は天候が悪く、トーンの暗い写真が多くなってしまった。 |
|
| |
|
 |
六呂師高原に到着。
ソフトクリームなどの乳製品の直売所がある。 |
| 右手建物ではソフトクリームを売っていたが、少し肌寒いくらいだったので食指が向かない。 |
|
| |
|
 |
六呂師高原全景。
山々は霞に包まれて映えないが、以前車で来たときは快晴で素晴らしい景色が広がっていた。 |
| それにしても広い駐車場である。 |
 拡 拡
|
| |
|
 |
福井県奥越高原牧場に立ち寄ってみた。 |
| 以前は牛が放牧されていた場所があったのだが見つからない。 |
|
| |
|
 |
越前大野へ戻る途中、前回訪れて通行止めだった林道法恩寺線のことを思い出して引き返す。 |
途中で再び戻り、右手の白い建物の手前から林道法恩寺線に入る。
福井県道26号の大野市側からは、小さいが林道の案内標識がある。 |

|
| |
|
 |
林道法恩寺線の大野市側入り口にはイノシシ進入(進出?)防止の電気柵とゲートがあって、通行者は看板の手順に従い、自己で開閉して通過しなければならない。 |
| このようなゲートのある林道も珍しい。 |
 拡大 拡大
|
| |
|
 |
電気柵の電線は3本あって、感電しないように碍子のある取っ手を持って外す。
通過したら再び元に戻す。
一番気を遣ったのは、3本ある配線を絡ませないように避けることであった。
何とか感電せずに通過できた(笑) |
最初は戸惑うことしかり。
それにしても、電気工学?に疎い人が無事に通過できるか否かは不明。 |

|
| |
|
 |
林道恩寺線の大野市側起点より4Km地点。 |
| 広域基幹林道法恩寺線は勝山側まで総延長26.4Kmある。 |

|
| |
|
 |
林道法恩寺線途中から見た勝山市方面。 |
| 悪天候なことが悔やまれる。 |

|
| |
|
 |
林道法恩寺線7.5Km地点 |
| 起点よりかなり走行したつもりが、総延長の1/3にも満たない。 |

|
| |
|
 |
勝山市との境にある林道恩寺線開設記念碑。 |
| 記念碑の近くに「まむしに注意」と書かれた立て札があった。 |
|
| |
|
 |
林道開設記念碑の前の道を挟んで反対側は整備された展望台があって、勝山市街が見渡せる。
これより勝山側は前回に走破しているので、同じ来た道を大野市方面へと引き返す。 |
| 近くには駐車場もあって、林道もよく整備されているので訪れ易い。 |

|
| |
|
 |
今回の最終目的地は、越前大野から国道157号を岐阜方面へ向かい、真名川ダム手前の佐開(さびらき)から奥越の名峰である荒島岳(標高1,523m)の佐開登山口へ続く林道を訪れる行程である。 |
| 佐開(さびらき)の西の外れに荒島岳の登山届けのボックスがあり、これより登山口に続く林道となる。 |

|
| |
|
 |
林道鬼谷線から途中の養魚場を過ぎたあたりから、支線林道を右手に入るのが事実上の登山口へ至る林道となるようだ。
訪問時は事前の確認を怠ったがために、道なりにまっすぐに進んでしまい林道鬼谷線の終端まで行ってしまった。
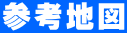 |
| 総延長4.9Kmとあるが、通り抜け不可のため往復を要する。 |
|
| |
|
 |
林道は途中に落石や断崖絶壁の危険な箇所もあるが、オフロードバイクであれば難なく走行できる。
乗用車はパンク覚悟なら走行できると思う。 |
一応舗装はしてある。
このあたりは写真撮影ができる余裕のあるところ。 |
|
| |
|
 |
林道鬼谷線の総延長4.9Kmのうち4Kmほど来た地点で、突如荒れた道となる。
危険な道を単独で1Kmばかり走って何かあってもつまらないので、ここで引き返し今回の旅の全コースを終える。
荒島岳登山口への正規の林道は、同年10月に再訪した際に判明したので、ご参照いただきたい。
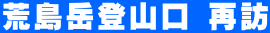
|
行ってみたい気持ちを抑え引き返す。
単独ツーリングの限界だが、ひとり旅愛好家なので仕方ない。 |

|
| |
|
 |
帰路も温見峠を経由する。
またもや雨模様だが霧雨で本降りでないことがありがたい。
それにしても幾度この峠を通ったことか。
一部の道マニアの方々は、この道を国道ならぬ「酷道」と揶揄され、通ることを罰ゲームの如く仰るが、自分にとっては自宅付近の市街路の方が遙かに危険な道に思えるのである。 |
数え切れないほど通った峠道。
ふと、青春時代に時間が戻ったような錯覚を覚える。 |
|
| 当初計画していた日が数日前の予報で雨天となっていたので一日遅らせた。これが見事に外れて当初の計画の出発日は快晴となったが今更変更はできない。運悪く曇天と小雨の中の行程となって、爽快感に浸ることはできなかった。しかも目的地の仙翁谷抗口や荒島岳佐開ルートに至る支線林道の入り口を見落としたのは事前チェックの甘さからであり、「せっかく行ったのに」という気持ちになる。でもこれで次回は、しっかり下調べをした上で再訪しようという理由ができた。年内に再び行けるとしたら9月中旬あたりだろう。バイクに積載可能な装備では10月過ぎの山での宿泊の寒さを凌ぐのは結構つらいのである。今回の旅でも8月下旬にあれど、東海地方より一足早い秋の気配を感じたのであった。 |
|
| 13 |
|